第八回「家庭教師・学習教材でトラブルに遭わないために」~消費生活アドバイザーから見た日本社会におけるギャップ~
《消費生活アドバイザーによるギャップ解決情報》第八回「家庭教師・学習教材」
<事例① 家庭教師>
中学2年生の息子の成績が思わしくないこともあり、投函チラシで知った家庭教師派遣会社に電話をかけ相談した。翌日この会社の担当員が自宅に来て、息子に学力テストをさせた。2日後、同じ担当員がきて、この学力テストの採点結果を見せながら説明を始めた。彼によれば、学校の定期テストの点数を上げるには、一学年下から振り返り学習が必要とのこと。また学校の学力テストは、この業者が作成した問題集の類似問題が多数出るとのことだった。指導内容の説明に魅力を感じ、家庭教師派遣と教材購入の一括契約をして教材費約50万円を業者宛に現金で送金した。
教材が届いたあと家庭教師が週一で自宅にきて息子の学習指導をしたが、契約時に説明していた振り返り学習をしないなど指導内容が違っていた。また、学校の定期テストは、購入した問題集の傾向とは違った問題ばかりだった。業者に電話して苦情を伝えたが、対処しますというばかりで改善されない。 また、息子はこの家庭教師が嫌いになったようで、友達と塾に通いたいと言い出した。業者への不信感が募り解約を申し出たうえ教材を一括して返還した。
その後、業者から中途解約料として約30万円を差し引き残金を返金するとの提案書が届いた。提案書には、「担当教師からは、家庭教師の指示通り勉強をしていないとの報告が上がっているので、契約規約通りの違約金を提示した」と書いてあった。 確かに、契約書には、解約時期に応じた解約手数料が定められていた。しかし事業者の問題集が学校のテストに全く役に立たなかったことや、説明通りの振り返り学習がなかったことなど、勧誘時の説明と違うので不満だ。(40歳代 男性 個人事業主)
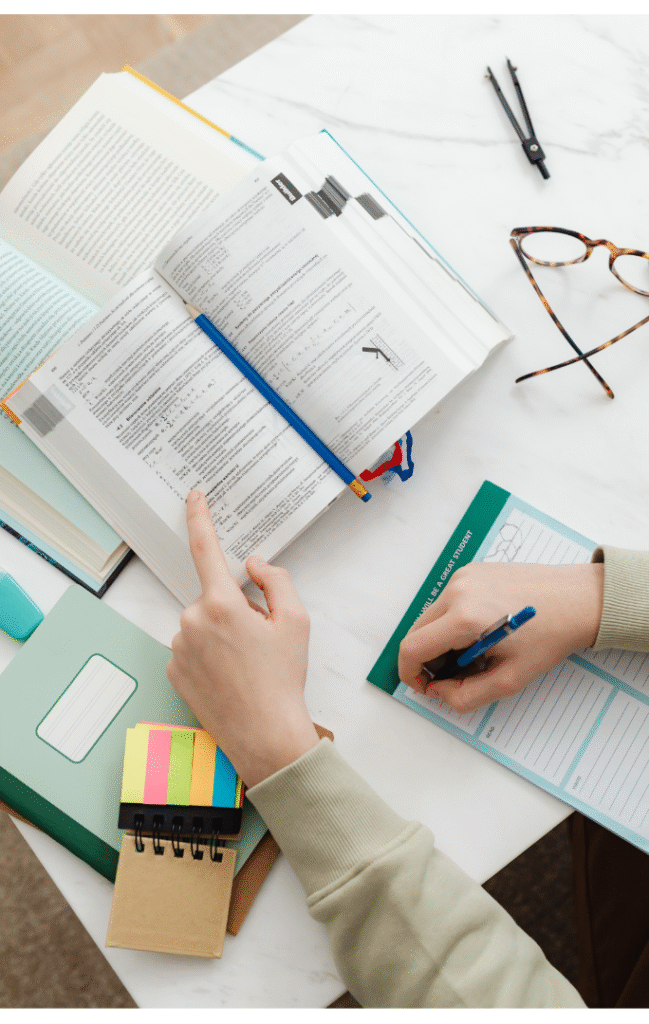
【注 意 点】
- 契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円以上であれば、特定継続的役務提供に該当します。特定商取引法の定める書面の受領日を1日目として、8日以内ならクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間が過ぎてしまった場合でも、法で定めた解約料を支払うことにより中途解約することができます。
- 中途解約までに提供された役務の対価に相当する額については消費者が負担することになります。また、中途解約に伴う損害賠償の額は上限が設定され、事業者は、これを超える額を請求することはできません。事業者が解約料を定める場合には合理的算出根拠が必要です。なお、これらに対する遅延損害金が生じた場合は、別途消費者が負担することになりますが、法定利率を超えた額を支払う必要はありません。
- 役務提供を受ける際に関連商品も一緒に購入されている場合はその関連商品も一緒に解除することができます。関連商品の価値が低下した場合「販売価額に相当する額から返還された時における価格を控除した額」、すなわち新品と返還された関連商品の中古品としての価値の差額分が「通常の使用料」を超えている場合にはその額が上限となり、書籍に書き込みをした場合のように、関連商品の返還時の価値が低下している場合には、契約締結時の交付書面に記載した清算方法に拠って、その差額分を上限として請求されることになります。(★参照:消費者庁・消費者への注意喚起)
<事例② 学習教材>
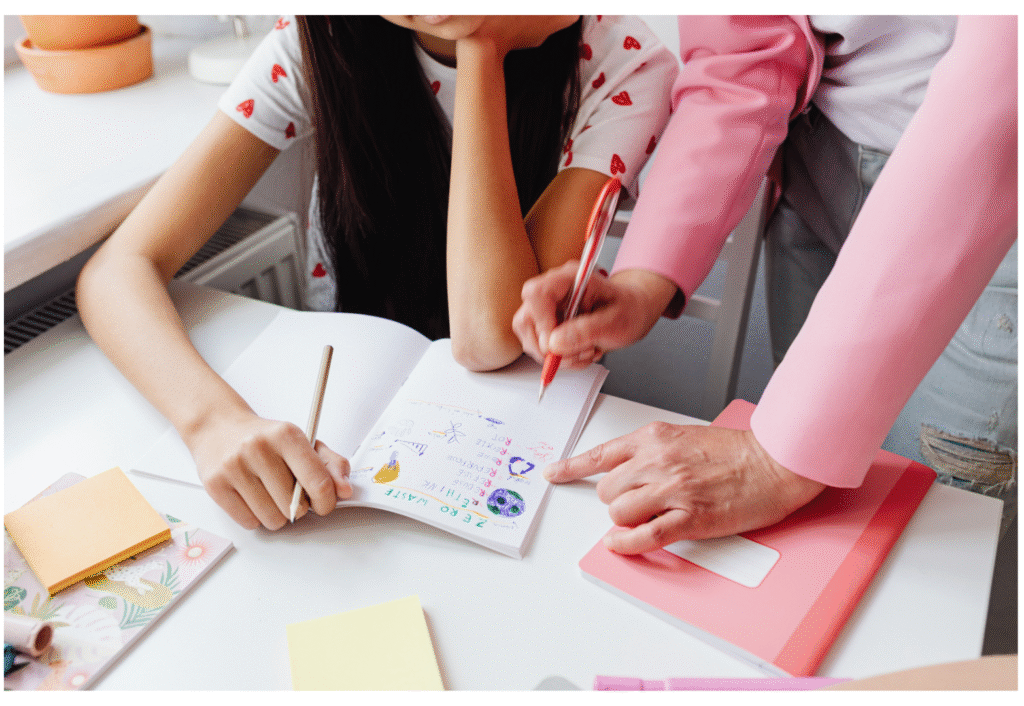
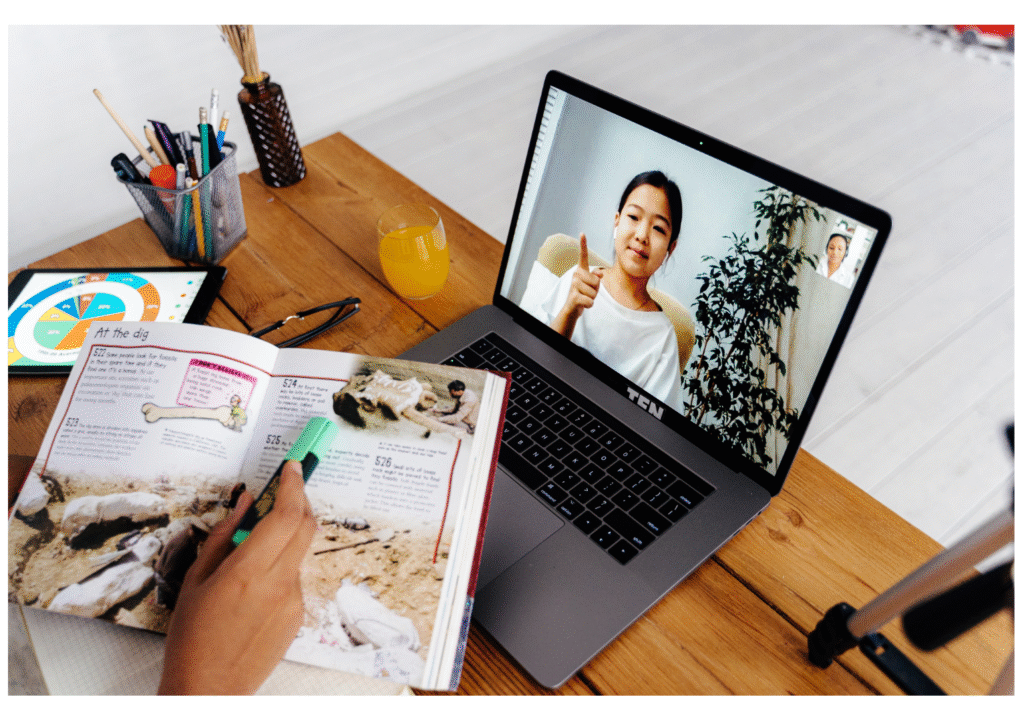
SNS広告で某学習教材に興味を持った。販売業者に自宅に来て貰い、小学6年生の娘に無料体験を受けさせた。その結果、業者訪問員が、「独自の学習教材は楽しみながら学習できるよう作成されている。お子さんの学力を平均値に引き上げるため3年間分の教材を一括して頼みましょう」と、中学3年間、5科目分の学習教材及びタブレット端末貸与の購入契約を勧められた。その際、教材を使用しなくなった場合は返すこともできると言われたため、安心して契約書に署名押印した。会員登録料 1万円と教材費80万円はクレジットカード12回払いで決済した。
契約後、娘にタブレット端末を使って自習させたが、途中から娘の興味が薄くなり、受講を嫌がったので解約することにした。学習教材業者に連絡して解約希望を伝えたが、その後は連絡がないため、教材及びタブレットすべてを教材業者宛に返品した。
5日後、契約解除合意書が届いたが、書面には、「学習教材の販売契約であり、タブレット貸与は付随サービスである。教材やタブレット機能に瑕疵がないことから会員登録料及び教材の返金には応じられない」と書いてあった。不満に思い、クレジットカード会社に抗弁書を提出し、いったん請求が止めてもらったが、数か月後に請求が再開されている。クレジットカード会社は、教材会社と話し合って解決してもらいたいとのことで、仲介してくれなかった。契約書の中途解約に関する条項を確認したところ「解約清算金算定時の契約期間は、3カ月間を最長契約期間として算出する」との記載があった。しかしこのような規定は契約前の口頭説明になかったので納得できない。(40歳代 女性 給与生活者)
【注 意 点】
- 売買契約では、重大な契約違反や契約書面の記載内容に不備がなければ、一方的に契約を解除することができません。従って契約書に書かれている解約条件に基づいて解除申し出することになります。事業者から提示された解約条件に納得できない場合は事業者と話し合うことになりますが、交渉は難航することがあります。
- 複数年分の教材の購入を勧められたとしても、それらの教材が実際に子供に合っているかどうか分かりません。契約を急がされても、その場で契約せずに、契約書の解約条件等について確認することが大切です。
- 契約を勧誘する際の事業者のセールストークの内容は、トラブル解決のときに重要な役割を果たします。契約を締結したときは、説明された内容を記録に残すようにましょう。巧妙な勧誘や広告につられず、サービスの内容、料金、解約条件などについて、事前に書面をもらって十分確認しましょう。
執筆者プロフィール 金崎賢秀(HN)
埼玉県在住。2003年消費生活アドバイザー資格取得。2005年民間保険会社を定年退職し、同年、地元自治体の消費生活センターで消費生活相談員に任用される。以来18年5か月勤務し、2024年3月末に退職する。現在は社会貢献活動として地元の複数の相談業務に参加。
趣味:各地の自然遺産の探訪。読書(推理小説を乱読)。1945年生れ。


