第六回「クレジットの不正利用」~消費生活アドバイザーから見た日本社会におけるギャップ~
クレジットカードの不正利用
「クレジットカード不正利用の被害」が急増しています。特にSMS(ショートメッセージサービス)やメールにより、パスワードなど個人情報が盗まれないよう気をつけましょう。
<事例①:クレジットカードの不正利用>
銀行口座残高を確認したところ、残高が大きく減っていた。WEBサイトでクレジットカードの利用代金明細を確認したら、数か月前、知らない販売会社名で約20万円の身に覚えのないカード利用があった。不正利用の疑いを持ち、カード会社にカードの利用停止を申し出たうえ、調査を依頼した。なおカードは、普段用いる財布とは別の財布に入れ自宅の棚に保管しており、貸与したこともなく、この数か月間はネット通販でカード決済していない。
カード会社による調査の結果、取引内容はノートパソコンの購入であるとのこと。注文者名は自分の名前が無断で使われおり、商品送付先や受取人は他県住所の知らない人宛てになっていた。 カード会社に返金を求めたが、規約に定める保証期間を過ぎているという理由で、補償はしないと回答された。カードで購入したとする販売会社に対し、不正利用時の会員 ID や会員登録内容などを尋ねたが、販売会社からは、当社では、不正利用かどうかの真偽は不明と回答があった。すでに利用代金は引き落とされ支払い済みだ。再度カード会社に返金申し出たが、「不正利用については期間の猶予をもって会員の保護を行っている。 加盟店から正常な売り上げとしてデータが到着し、口座振替を終了したものであり、加盟店には国際ブランドを通して、精算が終了している。 上記により、当社としては返金には応じかねる」との回答があった。あきらめるしかないのか。(50歳代 女性 給与生活者)

【注 意 点】

- SMSやメールを通じて、事業者や公的機関などがいきなりクレジットカード番号の入力を求めることはありません。日頃利用している事業者等からのSMSやメールでも、まずフィッシングを疑い、ID・パスワード、クレジットカード番号等は絶対に入力しないでください。
また、日ごろからご利用明細をよくご確認いただき、身に覚えのない請求があった場合はすぐにカード会社に連絡しましょう。不正利用に気づいた後、直ちに最寄りの警察に被害届を提出する必要があります。 - 不正取引の対象である販売会社に対し、ネット取引の受注・出荷明細を提出するよう求め、受注・出荷明細が提出されたら、カード会社に、上記確認事項を示して再調査を依頼するという方法もあります。
- カード会社には、支払明細が確定した旨を知らせるメールの詳細、売上票の詳細、決済時にどのような情報が入力されていたか、 本人認証方法の確認、3D セキュア認証利用の有無の確認、決済代行会社における不正探知システムでアラートがあったことの認識の有無の確認を求めること。その後、カード会社から提供された資料を踏まえて再度警察に出向き、再度調査依頼をすることにより、カード会社は、本件カード利用については不正利用であると判断してもらえる可能性があります。
【参 考】
「フィッシング」とは、実在のサービスや企業をかたり、偽のメールやSMS(携帯電話のショートメッセージ)で偽サイトに誘導し、IDやパスワードなどの情報を盗んだり、マルウェアに感染させたりする手口です。情報を盗まれると、アカウントを乗っ取られてお金を奪われたり、インターネット通信販売サイトで勝手に買物をされたりします。
また、マルウェアに感染してしまうと、スマートフォンに登録された電話帳の情報が盗まれたり、自分のスマートフォンがフィッシングSMSの発信源になってしまうこともあります。(警察庁HPより)

<事例② クレジットカード盗難による不正利用>
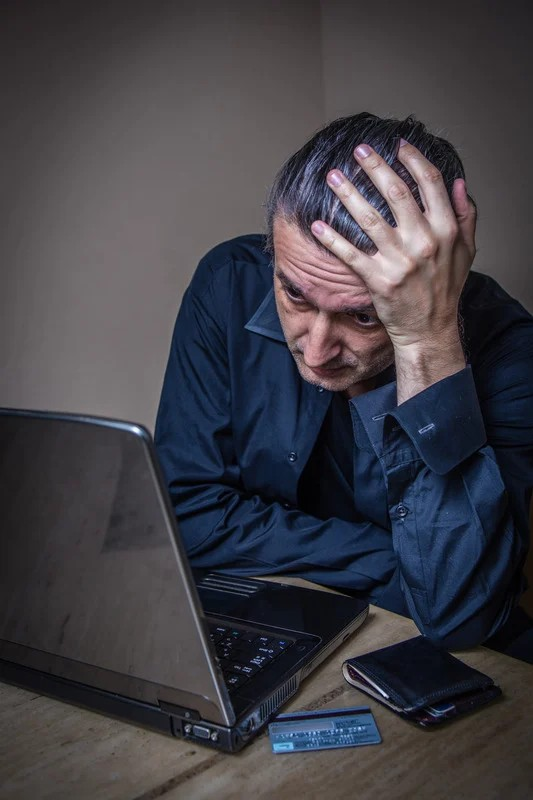
過日、乗車した電車内でカバンを何者かにひったくられた。カバンの中には、クレジットカード、銀行のキャッシュカード、運転免許証、健康保険証などが入っていた。自宅の最寄り駅で遺失物届を出して帰宅し、クレジットカード会社、銀行に連絡し、すべてのカードの利用を止めた。翌日、警察署で窃盗の被害届を出した。警察官の助言に従い、クレジット会社に補償申請の連絡をしたところ、クレジット業者からは、「合計約30万円の複数の決済が確認された。しかし、パスワード取引であるから補償できない」との回答があった。
不満に思い、パスワードの分かるものはかばんに入れていないはずなので、不正利用分の請求に間違いないと、再度補償要求した。クレジット会社は「すべての取引において正しいパスワードが 1回目で入力されていることから、事前に本件カードの暗証番号を認識していたと考えられる。加えて、カードのパスワードは当社に登録した生年月日の下4桁と同一の数字であり、このような日常的に使用する番号は他人が推測しやすいパスワードに該当する。暗証番号管理に関する善管注意義務違反があったことは明らかである。従って、カード盗難による損害であったとしても、当社のカード規約に基づき、申請人の負担となる。請求を認めない。」と回答してきた。
不正利用であってもクレジットカード会社が補償してくれないのは納得できない。(29歳 男性 給与生活者)
【注 意 点】

- 一般的に他人に容易に推測され得る番号(例えば生年月日や電話番号等)を暗証番号として設定していることは、カード会社の規約にて管理注意義務違反になると同時に、消費者には過失がないと主張する根拠が弱くなるので注意しましょう。
- クレジット会社の規約の中には、暗証番号取引の場合、会員の無過失をクレジット会社が認めない限り会員負担と規定されていることが多いです。
このことから消費者契約法に触れるという主張もできますが、暗証番号管理における申請人の過失の有無や規約の問題については司法判断に委ねることになります。 - 警察で盗難届が受理されていることや、かばんのひったくりであることから犯罪性が高いこと、他の盗難にあった他社のカードについて、不正利用を受けた金額の一部の金額補償を行っている事業者の事例がネット検索でも散見されることなどの状況を伝え、クレジット業者に再交渉するという方法もあります。
執筆者プロフィール 金崎賢秀(HN)
埼玉県在住。2003年消費生活アドバイザー資格取得。2005年民間保険会社を定年退職し、同年、地元自治体の消費生活センターで消費生活相談員に任用される。以来18年5か月勤務し、2024年3月末に退職する。現在は社会貢献活動として地元の複数の相談業務に参加。
趣味:各地の自然遺産の探訪。読書(推理小説を乱読)。1945年生れ。


